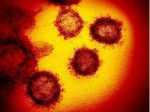「医師会に気遣い、後退」と産経11月28日に開かれた社会保障審議会の2つの部会で、厚労省は介護と医療のサービス提供の新判断を示した。制度の土台に関わる重大事だが、共に先送りとした。 介護保険改定では、介護保険部会開催の翌29日に「2割負担拡大」(朝日新聞、読売新聞)、「ケアプラン有料化先送り」(東京新聞)と予想通りの内容を報じた。出遅れた毎日新聞は、次の部会後の6日に後追いした。給付抑制・負担増の議論は日本経済新聞が6日に「23年に持ち越し、異例だ」、朝日新聞は9日に「法改正が必要な見直しは24年度実施を断念」と厚労省の姿勢を冷ややかに記した。当初7つの見直し案を提示した同省。姿勢転換を両紙はきちんと総括した。一方、コロナ禍で不評の「かかりつけ医」問題は29日、読売新聞、産経新聞、東京新聞が「かかりつけ医 法に明記へ」と医療部会の厚労省案をそのまま伝えた。朝日新聞は「かかりつけ医 書面で確認可」と対象患者との関係に拘った。日経新聞だけは、法への明記は「具体的な責務規定はない」と指摘し、「認定制は見送り」「医師の自主性に委ねる 大病院との分担見通せず」と先送りを批判した。 さらに、踏み込んで「制度設計の後退許されぬ」とこき下ろしたのは4日の産経新聞の社説「主張」だ。全世代型社会保障構築会議が11月11日に示した「手上げ方式」のかかりつけ医活用案からの「後退」と断じた。その原因は「制度化や登録制に反対する日本医師会に気遣った」と言及。同紙は「登録や認定制の導入が必要」と訴える。全体の構図を解き明かした秀逸な「主張」である。読売新聞が11月27日から7回連載した「続・コロナ禍の傷跡」は提言型のいい企画だった。病院や施設の面会謝絶で心の傷を負った家族たちの声をすくい上げ、「最期の時間共有を拒絶する医療とは何か」と考えさせる。医師側からの弁明を聞きたいが、医療機関の固有名詞がなく残念だ。11月23日の東京新聞は「『生活援助』担い手増えず」「30都府県 研修開催ゼロ」と、厚労省が創設した「生活援助従事者」の実態を報じた。59時間の研修で資格者となるが、介護保険の身体介護ができないので敬遠されがち。当然だろう。そもそも現場無視の机上プランではないだろうか。日経新聞は11月3日に「成年後見進まぬ利用」「市民後見人の育成急務」と後見制度の欠陥を突いた。認知症ケアの一環として重要な制度なのに、司法関係者と現場のズレがここでも起きている。浅川 澄一 氏 ジャーナリスト 元日本経済新聞編集委員1971年、慶応義塾大学経済学部卒業後に、日本経済新聞社に入社。流通企業、サービス産業、ファッションビジネスなどを担当。1987年11月に「日経トレンディ」を創刊、初代編集長。1998年から編集委員。主な著書に「あなたが始めるケア付き住宅―新制度を活用したニュー介護ビジネス」(雲母書房)、「これこそ欲しい介護サービス」(日本経済新聞社)などがある。