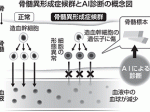東日本大震災後の10年間で宮城県内でお産を扱う病院などが3割減り、特に仙台医療圏以外は半減したことが分かった。沿岸部では複数の分娩(ぶんべん)施設が津波被災により閉院した。一方で産科医不足は地域を問わず、分娩施設の減少に歯止めがかからない。(報道部・菊池春子) 県によると、震災前から10月までの分娩施設数の推移はグラフの通り。県内4医療圏のうち、仙台市を含む14市町村がエリアの仙台医療圏は29から約1割減の25。一方、仙台圏以外の内陸や沿岸部は22から11に半減した。石巻市では2施設が津波被害の影響で閉院し3カ所となったほか、気仙沼市では1施設が分娩を休止し、お産を扱うのは市立病院のみとなった。 産科医不足も深刻だ。白石市など9市町がエリアの仙南医療圏では2016年の公立刈田総合病院(白石市)に続き、みやぎ県南中核病院(大河原町)が今月、分娩を休止した。10年に8カ所あった仙南の分娩施設は、柴田町の2カ所のみとなった。 震災による周産期医療への影響を調査した東北大東北メディカル・メガバンク機構の菅原準一教授(周産期医学)は「少子化などで全国的に分娩施設は減少傾向にあるが、宮城は震災で加速した」と指摘する。 助産師の確保や育成などの課題もあり、菅原教授は「中途半端な体制では安全なお産を守れない。人材が限られ、一定の集約化は避けられない状況だ」と話す。 仙台医療圏へのお産の集約化傾向が強まる中、地域の住民や医療現場への影響は少なくない。 石巻赤十字病院(石巻市)は、市内の医院の被災や、登米市唯一の施設が19年3月末で分娩を休止した影響を受け、10年に664件だった出産数が19年は730件へと約1割増えた。 吉田祐司産婦人科部長は「多くの患者が集中するようになり、病院の設備が追い付かない。スタッフが変化に対応するのが難しい部分はある」と話す。 身近な分娩施設の休止により、自宅から1時間近くかけて通院するケースが相次ぎ、特に冬場、出産間近の妊婦の不安は大きい。早めに入院し、計画分娩を行うケースもあるという。 吉田部長は「産科や小児科は身近さが求められ、集約化だけで解決できない面がある」と指摘し、仙台圏だけに医療資源を集中させない取り組みの必要性を強調する。 県は、震災後の16年に仙台市に新設された東北医科薬科大医学部に通う県の奨学生が産科・小児科医になる場合、地域の病院勤務の義務年数を10年から8年に短縮し、希望者を増やしたい考えだ。 県医療政策課は「住民の負担軽減は課題だが、医師確保は容易ではない。さまざまな対策で医療体制の整備を図りたい」と説明する。◇ 東日本大震災と東京電力福島第1原発事故から来年3月で10年。被災地の復興の現状や課題に光を当て、「焦点」のタイトルで多角的に検証する。