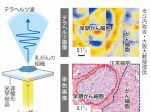新型コロナウイルスの感染拡大により、世界中の医療現場で需要が急騰した人工呼吸器。3月以降、米ゼネラル・モーターズ(GM)などの自動車メーカーや、欧州エアバスなど航空機大手も各国政府の要請を受けて生産支援に取り掛かってきた。日本国内で、異分野ながら人工呼吸器の量産を始めたのが自動車部品大手のマレリ(旧カルソニックカンセイ、さいたま市)だ。7月1日、埼玉県本庄市の児玉工場で製造した新型コロナウイルス感染者向けの人工呼吸器が、ボリビアやベトナムに初出荷された。もちろん人工呼吸器を一から開発したわけではない。マレリが担うのは部品の調達や製品組み立て、検査工程など。タッグを組んだのは、埼玉県川口市にある人工呼吸器メーカー、メトランだ。1984年にベトナム出身の新田一福会長が創業したメトランは、人工呼吸器を専門に扱う従業員47人の町工場。新生児や未熟児の繊細な呼吸量にも対応できる独自技術を持ち、今では国内の新生児集中治療管理室(NICU)の約9割で同社の製品が使用されているというパイオニアだ。国内では、MRI(磁気共鳴画像装置)や血圧計といった医療機器を製造するメーカーはあっても、人工呼吸器など患者の命に関わる製品を手掛ける企業は少ないのが現状。そんな中、同社は一貫して人工呼吸器の開発を続けてきた。生産台数は年間100台程度と小規模ながら、国内での製品需要は一旦落ち着き、最近では徐々に海外市場を開拓しつつあった。そんな中、新型コロナウイルスの感染拡大によって状況が一変する。医療現場で人工呼吸器の需要が急増し、同社のもとに世界中から数万台規模の問い合わせが届くようになったのだ。ただ、メトランは注文を受け1台ずつ手仕事で組み立てる生産方式。急な増産に応えられる体制は整っていなかった。そこで組んだのがマレリだ。2社が初めて顔を合わせたのは4月末。国内の人工呼吸器生産体制を整備しようという経済産業省の働きかけにより出会ったのがきっかけだ。■2週間で生産ライン4月から5月にかけて自動車各社は大規模な生産調整を進めていたため、1次サプライヤーであるマレリも生産ペースが落ちていた。人工呼吸器の製造に回せる社内の生産能力は十分にあり、急ピッチで量産に向けたプロジェクトが動き出した。普段は自動車のパワートレーンやコックピット部品などを手掛けるマレリ。医療分野での経験はほとんどなかったが、まずは自社の調達網を駆使し、量産向け部品の確保に取り掛かった。緊急事態宣言下で取引先との連絡や調整に苦労しながらも、部品は集まり始めた。ただ、どうしても患者の呼吸検出に使うセンサーケーブルをドイツのメーカーから買うことができない。欧州でも人工呼吸器の増産が進められていたため、そのドイツメーカーに部品が余っていないことが理由だった。そこで、電子部品の開発・生産も手掛けるマレリがセンサーケーブルの製造も請け負うことで、必要な部品を何とかそろえることができた。マレリの児玉工場内で研修スペースとして使われていた部屋の一角に、2週間ほどで人工呼吸器の生産ラインを急造。両社が出会ってから2カ月後の6月25日には量産を始めた。自動車の部品は通常、1~2年単位で開発が進められることが多い。マレリ常務執行役員の石橋誠氏は「強い使命感のもとで組織の壁を取っ払い、経験したことのないスピードで準備ができた」と話す。今回開発された人工呼吸器「Eliciae MV20」は、新型コロナウイルスの感染者専用に設計されたもの。「自発呼吸ができない場合」「呼吸が浅く酸素が不十分な場合」「人工呼吸器を外してもよいかモニタリングする場合」の3つのモードに簡素化したことが特徴だ。コロナ禍で混乱する現場では、誰が人工呼吸器を取り扱うかも分からない。高度で複雑な機械は事故のリスクにもつながるため、呼吸器の専門医以外でも、簡単に扱える仕様を心掛けた。また、設計をシンプルにしたことで、通常は1台数百万、時には1000万円以上する価格を10分の1程度に抑えることができた。メトランの中根伸一代表取締役副会長は「この人工呼吸器はビジネスとしてもうけるためではなく、社会的な意義を感じて取り組んでいる」と話す。新興国をはじめ、必要なところに必要な台数を届けるための価格設定を実現させた。現在は7~10人態勢で月に1000台程度を生産する。今後は第2波、第3波の感染拡大に備え、月に4000台程度まで生産できる体制を整えていくという。日本国内は今のところ既存の集中治療室(ICU)でカバーできているため、まずはメキシコなど人工呼吸器不足がより深刻な海外に向け順次出荷していく予定だ。コロナ禍で大手メーカーによる医療関連物資の支援や生産が相次いでいるが、マレリの石橋氏は今回の提携について「我々が生産支援をしているのではなく、メトランさんに仕事をいただき支援してもらっている」との思いを話す。雇用の維持にもつながるうえ、ユーザーに届く完成品を作り、社会貢献ができることに対して、社員がやりがいを感じているのだという。図らずもコロナ禍で結実した大企業と町工場のオープンイノベーション。「異分野で組む」「即決してスピーディーに進める」など、平時の課題を飛び越える力強さがそこにはあった。本格的な経済回復に向けてはこれからが山場だ。企業には、なりふり構わずチャレンジする大胆さが求められている。(日経ビジネス 橋本真実)[日経ビジネス電子版 2020年7月10日の記事を再構成]